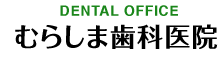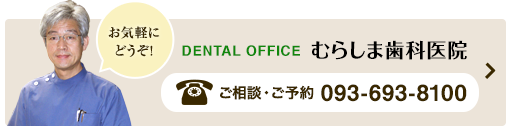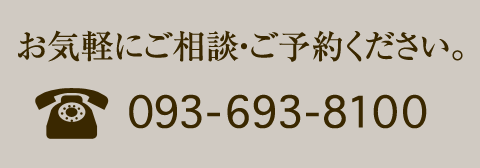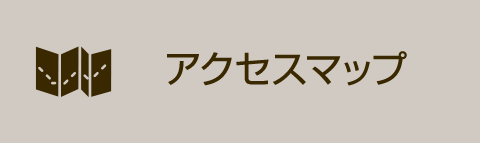歯周病治療
歯周病発祥のメカニズム
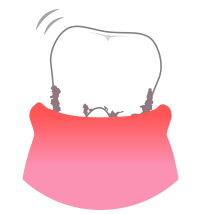
歯周病は、細菌によって引き起こされる感染症です。細菌の塊が歯ぐきや、その間、歯周ポケットに溜まります。
細菌の毒素によって歯肉が炎症を起こし、やがて歯ぐき周辺の骨や組織が破壊され、最後には歯が抜け落ちてしまう病気です。
お口の中には約900種類の細菌が住んでいます。その内、数十種類が歯周病に関係している菌です。
その中で最も悪いと言われているのがレッドコンプレックス(Red Complex)と呼ばれる、P.g.菌、T.d.菌、T.f.菌の3種と、A.a菌の合計4種です。
歯周病菌(歯槽膿漏)は全身、他の病気にも影響を及ぼします
◆動脈硬化を引き起こす原因に
歯周病が悪化することで、血管に歯周病菌が侵入し、
血流が悪くなり、動脈硬化を引き起こすと考えられています。
動脈硬化が進むと、狭心症や心筋梗塞、脳卒中のリスクが高まるのです。
◆歯周病と糖尿病の密接な関係
最も歯周病と深い関わりのある病気が糖尿病です。
歯周病が悪化することで炎症物質が増加します。
このうち、「TNF-a」は血糖値をコントロールするインスリンの働きを低下させてしまうのです。
歯周病によって、糖尿病の発症・悪化を招き、すでに糖尿病の方は免疫力が低下していることから
さまざまな合併症を引き起こす原因ともなります。
◆妊娠中の方は早産・胎児にも影響が
歯周病による炎症物質のひとつ「プロスタグランジン」という物質には陣痛促進作用があります。
このため早産を引き起こす場合があるのです。
また、歯周病菌が子宮に侵入することで胎児の発育を妨げ、低出生体重児出産に繋がりやすくなるのです。
一方で、妊娠中は歯周病にかかりやすい状態にあります。
さらに、つわりによって歯みがきが辛くなることも。
妊娠中の大切な時期だからこそ、しっかりとオーラルケアに取り組みましょう。
◆歯周病菌による感染症も
歯周病菌が他の部位に飛び火することで、肺炎やリウマチ、心臓病などにも
非常に関係が深いことがわかっています。
歯周病治療の流れ
歯周病の治療は2つの方法で行っていきます。
「歯石を取ること」
「正しいブラッシング」
この2つが重要です。
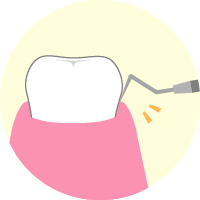
◆主な検査方法
- プローブという器具を使って歯周ポケットの深さを調べるプロービング検査
- エックス線写真で歯の支えとなる骨の状態を調べるレントゲン検査
- 歯周病の病原となる汚れ(プラーク)の状況を調べる検査
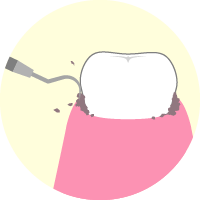
歯ぐきの上、見える部分に付着している歯石を取り除いていきます。
また正しい歯磨き方法の指導、糖を控えた食生活の改善を行い、歯肉の炎症改善を待ちます。
歯ぐきの炎症が改善されているか、検査を行います。回復していれば重症化予防に移ります。(定期検診など)

歯ぐきより下の歯石を取り除き、歯根の表面をなめらかにして行きます。
毎日のブラッシング、食生活の改善をしっかりと行い、歯ぐきの改善を待ちます。
検査を行い、歯ぐきが回復していれば安定期治療に移ります。
治療終了後も良好な歯周組織の状態を維持するため、スケーリング、プラークコントロール、PMTCを継続して行きます。
PMCTとは……プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニングの頭文字で、歯科医師・歯科衛生士などの専門家による歯の掃除のことです。
普段ご自分では磨けない部分もきれいに掃除するため、歯周病や虫歯を予防するのに効果があります。
歯ぐきを切開して、歯石を除去します。
検査を行い、歯ぐきが回復していれば安定期治療に移ります。
メンテナンス(長期管理)へ
定期検診によって、予防・悪化を防いで行きます。